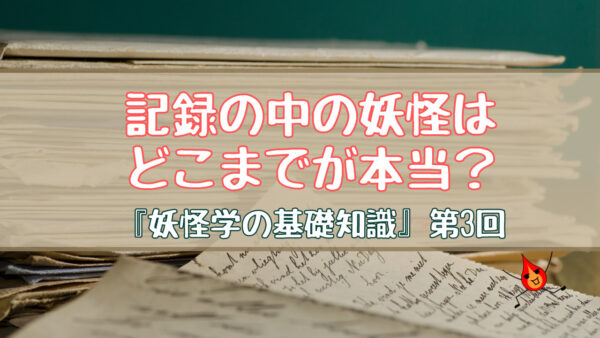
第3回目のテーマは「記録の中の妖怪」です。妖怪が描かれ、紹介されてきた書物は古代から多数存在しますが、それらの記録はどこまで信憑性があるものなのか、その見極めはどうするのか、について論じられています。 こちらの章は古代民俗研究所所長の大森亮尚(あきひさ)さんが担当されています。
この章で扱うのは、明らかな「物語」ではなく、『日本書紀』や『続日本紀』などの史書となります。もちろん、これらも全てが歴史的事実であるわけではなく、神話や伝説なども含まれてはいますが、そこを極力排除しながら、史書の中の妖怪たちの信憑性を探っていきます。
『日本書記』に現れる怪異
著者は歴史的事実として確認できる時代を「西暦600年代の第33代推古天皇あたりが妥当」としています。それに従い、西暦600年代をスタートとして、歴史に沿って妖怪達が起こしたと思われる怪異の数々を追っていきましょう。
この時代以前の神話時代には、怪異と人間の世界の境界は曖昧で、神々や精霊、さまざまな怪しいものが主役となる時代でしたが、この時代になると、人の世がメインとなり、そこに現れる珍しい怪異が記録として残されるようになってきます。
- 619年 摂津国(今の大阪・兵庫のあたり)の堀江に仕掛けた網に魚でも人でもない、子供のような形をした何かが掛かっていた。
- 627年 陸奥国(今の福島、宮城、岩手、青森あたり)に狢(むじな)が人に化けて歌をうたった。
- 637年 大きな星が雷のような音を立てて東から西へ流れていった。皆は流星の音だと騒いだが、ある僧侶が言うには、流れ星ではなく天狗が吠えた声だという。この天狗は我々のよく知る鼻の高い妖怪ではなく、「アマキツネ」と呼ばれた天空にいる妖怪らしい。
1-1空を飛ぶもの
『日本書記』に記された妖怪は、天空を飛翔するものが多いようで、655年には以下のようなものが空を駆け巡ったという記録があります。
- 竜に乗った者が大空を飛翔し、その風貌は唐人に似ていた。青い油の笠を着て、葛城山から飛んで生駒山の方に隠れ、昼頃になって難波の住吉神社付近の松嶺というあたりから西に向かって飛び去った。
これは一体なにを描写したものだったのでしょう。「青い油の笠」というのは防水用の油を塗った青い絹で作った雨具で、合羽に似た唐風の装束だったのだそう。日中に目撃されており、その姿が克明に報告されているが、ここではその正体ははっきり判明していません。
しかし、『続日本記』の中で役小角(えんぬおず)という、葛城山から空を自由に飛び回ったことで知られる実在の人物が記されており、筆者はこの役小角の若かりし日の姿だったのではという仮説を立てています。
1-2鬼・鬼火
661年、斉明天皇の最期にあたって、次のような不思議な出来事が記されています。
- 斉明天皇が朝倉山(福岡県)で崩御の際、こうたい皇太子・中大兄皇子が天皇の遺体に付き添い磐瀬宮に還ったが、この夕べ、付近の朝倉山の上に鬼が現れ、大笠を着て、その喪儀のさまを臨み見ていたので、人々は皆怪しんだ
実はこの2ヶ月ほど前から怪異は現れており、この頃天皇は磐瀬宮から朝倉山に遷ったのだが、宮造りのためにその地にあった木を切り払ったところ、神の怒りを買い、宮殿が破壊されたとあり、その上、次のようなことも起こったようです。
- 宮の中に鬼が現れ、これによって大舎人や宮人などが多く病死した
この神、鬼、そして朝倉山に現れた大笠を着た鬼とは一体何だったのでしょうか。
筆者によると、これらは雷神だったのではないかと述べています。落雷により宮殿が破壊され、朝倉山での大笠を着た鬼も山頂で稲妻がきらめいたものを見たのではないか、というものです。
確かに雷は現代でも目の当たりにすると身がすくんでしまうような恐ろしい現象なので、神の鎮座する山として民俗信仰のあった朝倉山で樹木を伐採したという事実も重なり、神の祟りを連想させたのかもしれません。
更に筆者はこの地域における特色についても触れており、『九州一円は隼人(はやと)や熊襲(くまそ)など大和朝廷に十分に服従していない人々が居住している地なので、(中略)そうした人々への警戒心や恐怖心が官人たちに朝倉山の鬼を幻想させたのだろうか。』と述べています。
1-3彗星
『日本書記』の中では、彗星に関する報告も複数記載されていますが、中でも変わっているものとして、678年に難波で報告された「甘露」を挙げています。
「甘露」とは、古代中国の伝承として伝えられる甘いつゆのことで、民衆に恵み深い政治を行った際に天が降らせるものとして伝わっています。
これが彗星かと言われると現在の彗星を知ってしまっている我々にとっては若干違和感がありますが、ここでは天から降ってくるもの、として捉えているようです。
ともかく、そのような甘い、そして見た目には綿のような物体が風に吹かれて松林などに翻ったという記録が残されています。
これを良い政治の象徴とされる「甘露」としていることから、当時の天武天皇の治世へのプロパガンダではないかと筆者は推測しています。
また、筆者はこれらの空飛ぶものが向かう方角にも注目しており、まずは以下のような記録がありますが、
- 682年 この年の8月は変異が続発し、3日の夕方には大きな星が東から西に流れ、5日は宮中の建物内に大きな虹がかかった。
- 682年 8月11日には火の色をした布のようなものが空に浮かび北に流れてゆき、国ごとに皆が目撃し、最後に越の国(北陸地方)の日本海の彼方へ消えていった。
これらは日本人の旅のあり方にも通じていると言います。すなわち、失恋・挫折すると北上し、最後の「死出の旅」は西方浄土へ向かうのと一致しているのだと述べられています。
『続日本記』に現れる怪異
ここからは『日本書記』から『続日本記』に世界に移ります。時代も移り変わってきますが、この中に記される妖怪で特徴的なのは、日本書記に見られたような妖怪達は出番がなくなり、代わりに皇位継承などの権力争いによる人間の妖怪化が見られるようになったことです。
1-1人間の妖怪化
まずは『続日本記』に記された以下の記録をご覧ください。
- 731年 紀伊国、阿氐(あで)群の海水が血の色に変色し、五日を経て回復した
この海が血の色に染まったという現象に関して、筆者は『日本霊異記』の説話を手がかりにある仮説を立てています。 海が血の色に染まる2年前の729年、時の左大臣・長屋王が謀反の嫌疑をかけられた挙句、夫人および四人の息子と共に自殺に追い込まれるという事件があった。『続日本記』によれば彼らの遺体は手厚く葬られたとされたとされていますが、『日本霊異記』での記載は違っており、彼らの遺体は城の外に捨てられ、焼き砕いて河に散らし、海に流された。長屋王の骨は土佐の国に流されたが、祟りなのか、その国の百姓たちに死ぬ者が多くなった。そこでその骨を紀伊の国の沖の島に移し置いたというものです。
この記述によって立てた筆者の仮説は2つあり、次のようなものです。
- 長屋王の死を藤原氏の陰謀であるとする反藤原氏の人々が、抗議のため、鯨やイルカなどの血を付近に撒いて怖がらせたのではないか。
- 沖の島付近の海が何らかの事情で血の色に染まることがあり、その原因を長屋王の悲劇に結びつけて語るという風聞が『日本霊異記』に取り上げられたのではないか
この二つの仮説のいずれかでも正しければ、この血の色に染まった海の謎は、不思議な現象ではないが、それでも朝廷内での争いの中で理不尽に殺されたさまざまな憎しみや恨みが引き起こした出来事であることには違いなく、そういった意味でもこの時代は人が怪異の元凶になり、なおかつその人自身も怪異そのものになってしまう伝承が多く残されているのです。
1-2死霊による現世の人間への祟り
ここからは、さらに人の恨みのこもった怨霊が登場します。
『続日本記』では妖怪に代わる恐ろしい「モノ」として、史書が半ば認めた怨霊の第1号とも言える人物のエピソードが記録されています。それが藤原広嗣(ひろつぐ)です。
広嗣は九州太宰府に左遷されていた藤原宇合(うまかい)の長男で、740年、当時朝廷で重宝されていた僧正玄昉(げんぽう)法師と吉備真備(きびのまきび)を排除せよという文書を朝廷へ送り、更に九州で反乱を起こしました(藤原広嗣の乱)。この反乱は朝廷軍によって制圧、広嗣は国外脱出を試みますが逮捕、処刑されます。
この反乱から6年後の746年、広嗣に批判されたうちの1人である玄昉法師が突然死しますが、その死に方が尋常ではなかったようです。
『続日本記』では次のように記されています。
- 世相伝えて云う。藤原広嗣が霊のために害せるところなり。
つまり、世間の噂ではあるが、広嗣の死霊に取り殺されたのだと伝えているのです。
詳細な状況を記している書物として『東大寺要録』がありますが、この中では「忽然と数丈も空に引き上げられてから落下して死亡し、血も骨もなかった」と伝えています。その他の書物でも空中で体がバラバラになり、その遺体が奈良まで飛んできたという説も残っているようです。
ホラー映画でもなかなか無いような凄惨さですが、この記録を裏付けるかのように、玄昉法師が左遷していた筑紫観音寺の講堂の裏手には「玄昉の胴塚」と呼ばれる石塔が今もあり、奈良の町には玄昉の首が落下して、それを葬ったという「頭塔」が存在し、更に腕が落ちてきたので地名になったという「肘塚町(かいなづかまち)」という町が存在します。福岡県と奈良県という、こんなに離れた土地同士で同様の伝承による塚が現存しているのは、なんともリアルさが感じられます。
また、『続日本記』には日本で初めての女性の怨霊ともいえる「井上内親王(いのえないしんのう/いがみないしんのう)」の記録も残っています。
井上内親王は聖武天皇の娘で、光仁天皇の皇后になった人物ですが、夫を呪詛した疑いで皇后の地位は剥奪され、息子と共に幽閉された挙句、775年に親子ともども不振な死を遂げます。この出来事から1年後、宮中では以下のような怪異が起こるようになります。
- 776年9月、20日ばかり毎夜、京中に瓦石土塊が降った。
- 777年3月、宮中でしきりに怪異があったので大祓をし、700名もの僧侶を呼んで読経させた。
ここでは怪異について詳しいことは書かれていないが、結末は次のように記されています。
- 777年12月と翌年の1月、二度にわたって井上内親王の墓を改葬し、彼女を元の二品の位に復位させた。
この年に起こった怪奇現象を井上内親王の祟りと認め、二度に渡っての改葬、復位を行ったという史実により、彼女は日本ではじめての女性の怨霊になったのだと言えそうです。
このように、史実の中にも、確かに存在するものとして記録される怪奇現象は多数あったようですが、史実に基づくものであればあるほど、その性質は妖怪から人間の怨霊へと変化していき、人間優先の社会に変化していくことを裏付けているとも言えます。




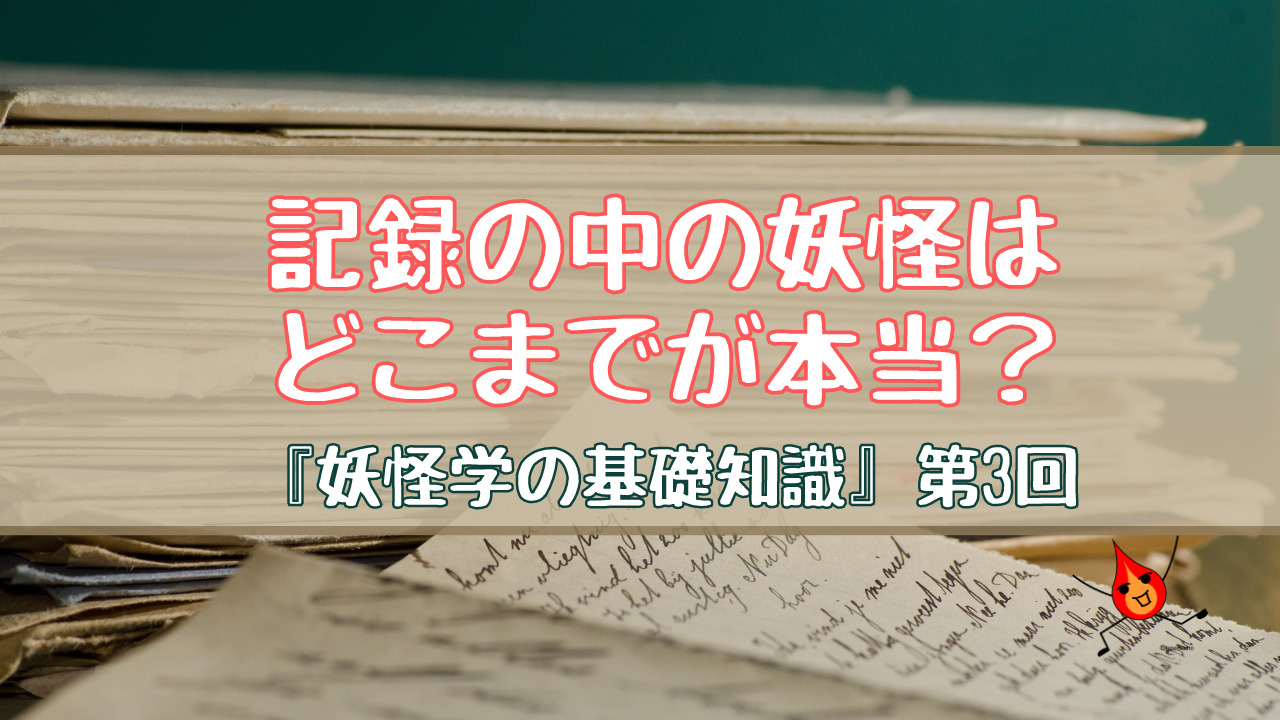
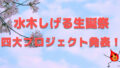
コメント